睡眠時無呼吸症候群のお話し
- 院長

- Apr 8
- 4 min read
◆ はじめに:その眠気、ただの疲れではないかもしれません
「夜はしっかり寝ているのに、朝からだるい」「昼間、会議中や車の運転中にウトウトしてしまう」そんなことが続いていませんか?
こうした症状がある場合、もしかすると「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気が原因かもしれません。この病気は、眠っているときに呼吸が何度も止まることで、脳や体に大きな負担をかけ、日常生活に支障をきたすだけでなく、命にかかわる病気の引き金になることもあります。
この文章では、睡眠時無呼吸症候群について、解説していきます。
◆ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
SASは、睡眠中に呼吸が10秒以上止まる「無呼吸」や、呼吸が浅くなる「低呼吸」が繰り返される病気です。これにより、体内の酸素濃度が低下し、何度も目が覚める(覚醒反応)が起こります。本人は気づいていないことも多いのですが、睡眠の質は著しく低下します。
◆ SASの主な症状
大きないびき
寝ている間に呼吸が止まる(家族に言われて気づく)
朝の頭痛やのどの渇き
昼間の強い眠気
集中力や記憶力の低下
イライラや気分の落ち込み
夜中に何度も目が覚める、トイレに行く
これらの症状は、「よくあること」「加齢のせい」と見過ごされがちですが、実は重大な病気のサインであることもあります。
◆ SASが引き起こす健康へのリスク
睡眠の質が悪いだけでは済まないのがSASの怖いところです。多くの研究により、次のような生活習慣病や命に関わる病気との関連が明らかになっています。
◆ 1. 高血圧
無呼吸により体が酸素不足になると、交感神経が刺激され、血圧が上昇します。これが一晩に何十回も繰り返されると、慢性的な高血圧につながります。
◆ 2. 肥満との悪循環
SASと肥満は、**互いに悪影響を及ぼす関係(悪循環)**にあります。
SASが肥満を引き起こす仕組み
無呼吸が繰り返されると、睡眠が浅くなり、ホルモンバランスが乱れます。
グレリン(食欲を増すホルモン)が増加
レプチン(満腹を感じるホルモン)が減少
その結果、つい食べすぎてしまい、太りやすくなるのです。
肥満がSASを悪化させる仕組み
肥満により、首やのど周りに脂肪がつくと、気道(空気の通り道)が狭くなり、息が止まりやすくなります。
◆ 3. 糖尿病との関係
無呼吸による酸素不足は、血糖を調整するホルモンであるインスリンの働きを悪くします。その結果、血糖値が高くなりやすくなり、糖尿病のリスクが増加します。
◆ 4. 心血管イベント(心筋梗塞・脳卒中など)
無呼吸により血圧が上がった状態が続くと、心臓や脳の血管に大きな負担がかかります。
心筋梗塞
不整脈
脳卒中といった重大な病気のリスクが上がります。
◆ 5. 認知症のリスク
近年、睡眠の質と**認知機能(記憶や判断力)**の関係が注目されています。SASにより酸素が足りない状態が続くと、脳の神経細胞がダメージを受け、認知症のリスクが高くなる可能性があります。
◆ SASの検査はどうするの?
「もしかして…」と思ったら、まずは医師に相談しましょう。SASの検査は、自宅でも受けられる簡単な検査から始められます。
◆ 第1ステップ:簡易ポリソムノグラフィー検査(簡易検査)
これは、小型の機器を使って、自宅で一晩寝ながら呼吸や酸素の状態を測る検査です。検査機関から検査キットが届きます。
この検査で無呼吸が疑われる場合は、さらに詳しい精密検査(PSG)に進むか、症状の重さによってはそのまま治療に進むこともあります。
◆ 精密検査(終夜睡眠ポリグラフ検査:PSG)
病院に一泊して行う検査で、呼吸だけでなく、脳波などを測定し、無呼吸のタイプや重症度を詳しく調べます。CPAP治療の導入を判断するために必要となることもあります。
◆ SASの治療方法
SASは、検査で正しく診断されれば、治療によって症状を大きく改善することができます。
① CPAP(シーパップ)療法
最も効果的とされる治療法で、寝ている間に鼻から空気を送り込む装置を使います。気道が閉じないように保たれるため、無呼吸がなくなり、ぐっすり眠れるようになります。
② マウスピース療法
軽症の方には、下あごを前に出すマウスピースを使って、気道を広げる方法があります。
③ 生活習慣の見直し
特に肥満がある方は、体重を減らすことで無呼吸が改善されることが多いです。
食事のバランス
定期的な運動
禁煙、節酒 など
◆ 放っておかないで、まずは一歩
睡眠時無呼吸症候群は、決して珍しい病気ではありません。しかし、気づかずに放っておくことで、生活習慣病や命に関わる病気を引き起こすリスクが高くなります。
気になった方は一度ご相談ください。よい睡眠は、元気な毎日への第一歩です。
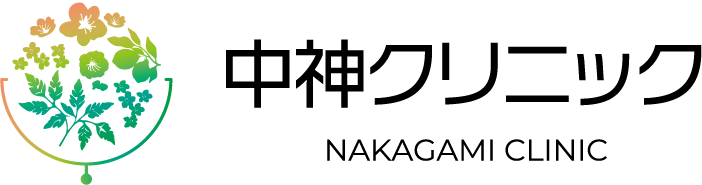





Comments